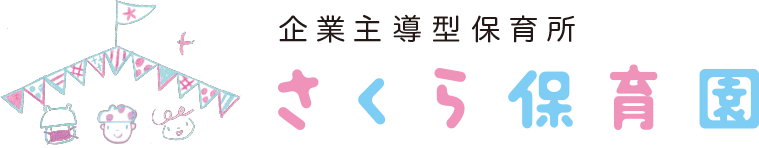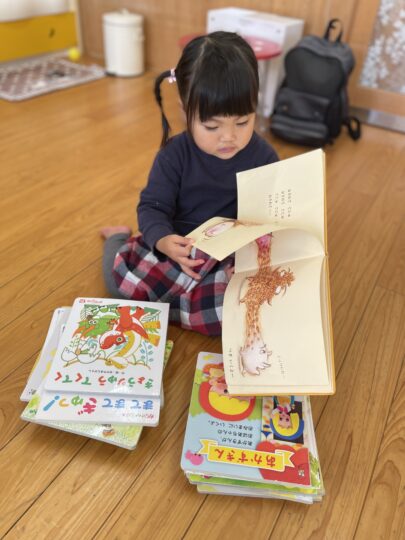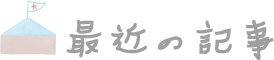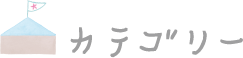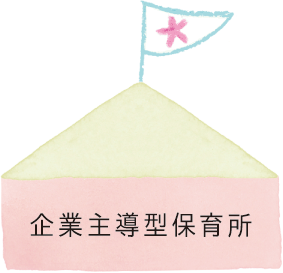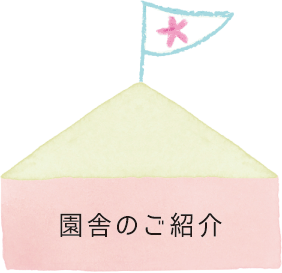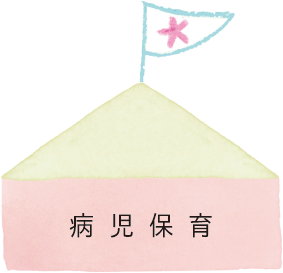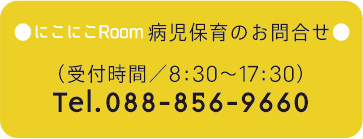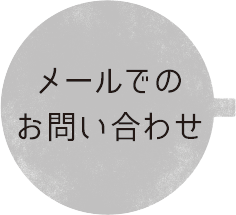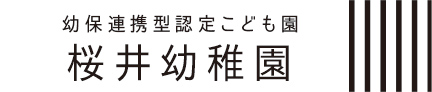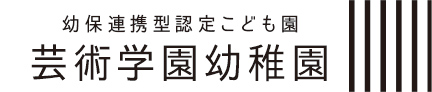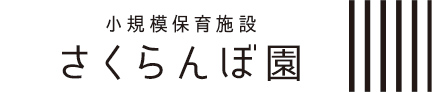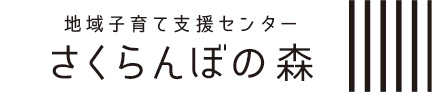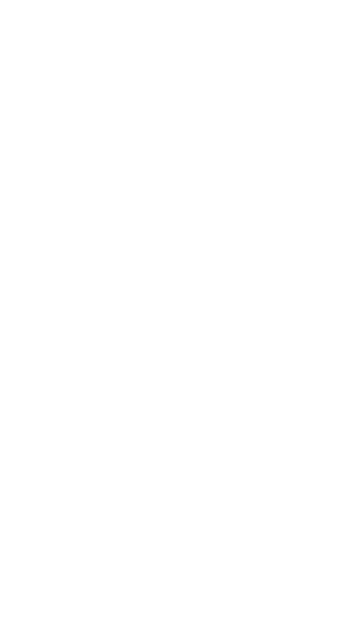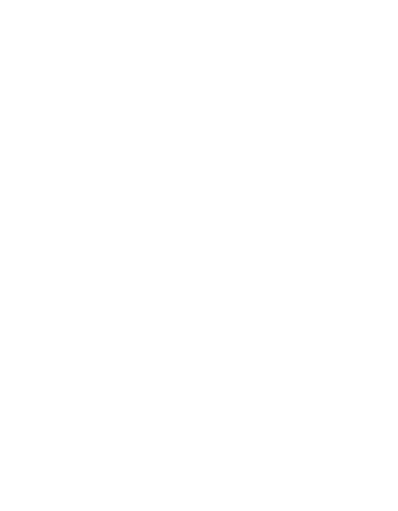
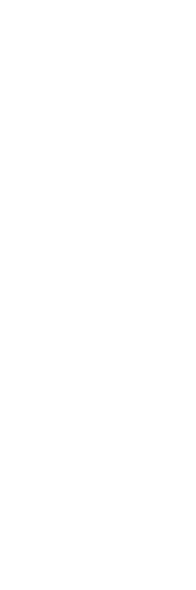
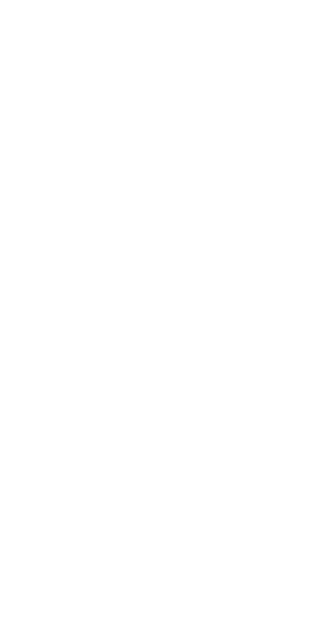


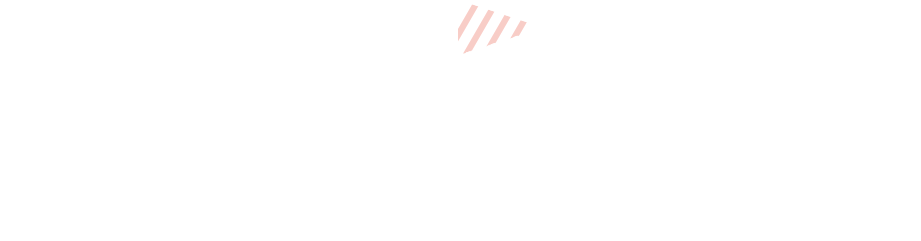
乳児期こそ、一人ひとりを大切に
2025.04.04
子どもは、一人ひとり違った輝きを持つ、かけがえのない存在。
そんな大切なお子さまを、家庭的な雰囲気の中、丁寧に関わり成長を支えていきます。
お母さんにも優しいサービスがいっぱい!
是非、園見学においでください。
*園内に同時在籍の場合、下のお子さまの利用料金は、無料です。
また、他園に兄弟が通われている第2子以降のお子さまは、
利用料金が半額になります。
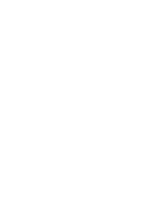

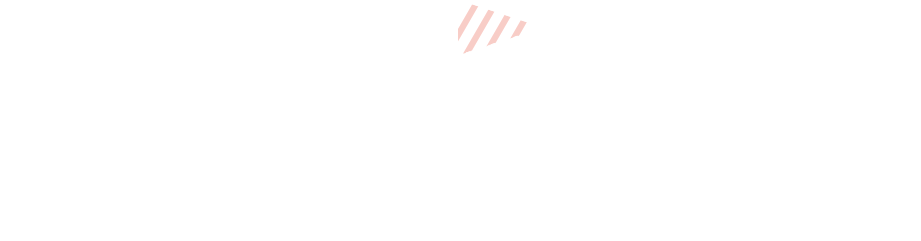
笑顔がとまらない!夏を満喫!!
2025.07.02
プール遊びが始まりました!
楽しすぎ!!笑顔がはじけます✨
「こっちも楽しいよ♪」それぞれの楽しみ方で、遊びます。
きゃー♡プカプカ気持ちいい!!
お水がかかっても ヘッチャラwww。


 「みて~、バチャバチャできる!!」
「みて~、バチャバチャできる!!」
思い切り水の感触を味わいながら、それぞれの興味関心に合わせて楽しんでいます!
水しぶきと笑い声、今日も元気に大爆発!
夏はまだまだ続きます☀あしたは何して遊ぶ?
この時期にしかできない体験を存分に楽しみたいと思います♬

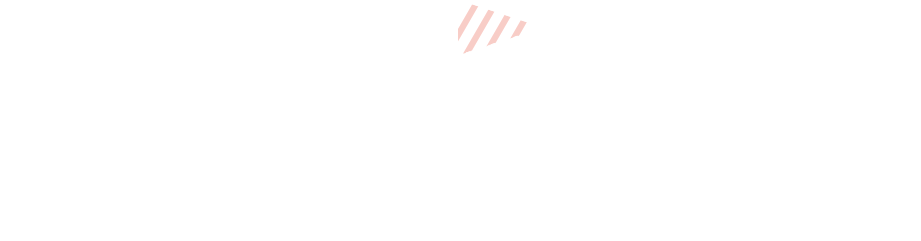
雨の日も楽しいね♬
2025.06.27
2歳児さんが、傘をさしてお散歩です。
準備は、OK!? みんなで 出発!!
いってきまーす!

 なにがいるかな~?かたつむり、おる?
なにがいるかな~?かたつむり、おる?
 くるくる コマみたいね♬
くるくる コマみたいね♬
 水たまりだ~💕
水たまりだ~💕

ちょっと つかれちゃったよ~💦 せんせい、かさもって~!

お花、元気かな?
ぴちゃぴちゃと水たまりを跳ねる音が、まるで笑い声みたいです♪
どんな天気の中でも、子どもたちは「楽しい」を見つける名人!
私たち大人も、そんな子どもたちの姿から、毎日たくさんの気づきと元気をもらっています☔✨
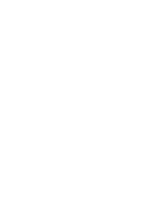

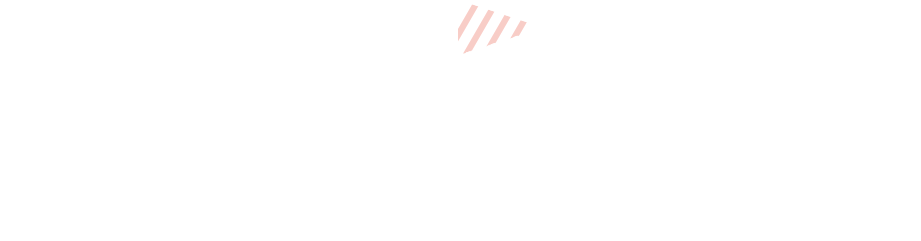
あそびは 小さな社会
2025.05.21
すれ違いも、こころが育つチャンス♪
先日の、ベランダでの水遊び。

アワアワいっぱい!ふわふわでいい気持ち♪

「ほらみて!アイスクリーム!」



色水遊びもしたよ♪

「うわ~!あおいろ!!」

「いちごジュースだ!」

「きいろになったね!」
目新しいものがみんな大好きなので、
とくに2歳児さんは、「じぶんが!じぶんが!」と、
どうしてもトラブルになりがち。
でも、そんな時でも、気持ちの折り合いをつけながら遊ぶ姿に成長を感じたことでした。

マイペースに遊ぶ0,1歳児さんたち。


子どもたちの遊びの中には、
小さな“社会”がたくさんつまっています。
思いを伝えてみること、
相手の反応にがっかりすること、
気持ちを切り替えること。
それらはすべて、「人と関わる力」の土台になります。
水遊びでの「じぶんが!」のぶつかり合いも、
自分の気持ちを出しながら、相手の存在を感じる大切なステップ。
うまくいったり、いかなかったりをくり返しながら、子どもたちは少しずつ、自分以外の誰かと一緒に過ごす力を育てています。
私たちは、その小さな関わりをあたたかく見守っていきたいと思っています♪

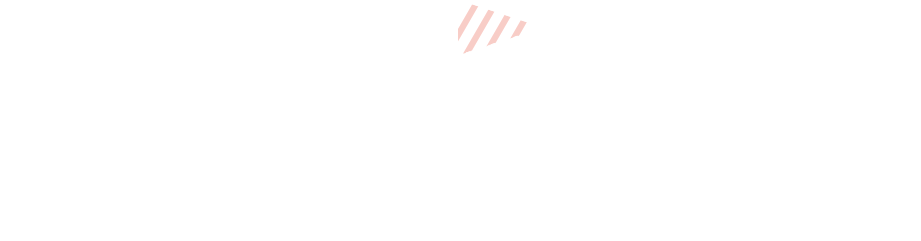
「ハイハイ探検隊、出発進行!」
2025.04.21
のびのびと、じぶんの“やってみたい”を大切に


暖かい日差しの中、公園でのびのびと遊ぶ子どもたち。まだ歩けない0、1歳児さんも、自分の行きたい方向へとハイハイで進み、興味のあるものを見つけては手を伸ばしたり、じーっと見つめたり……。その姿はとてもいきいきとしています。




子どもが“自分でやってみたい”という気持ちを持ち、環境に主体的に関わっていくことが、心と体の発達の土台となります。

のびのびと、探索活動を楽しませてあげたいですね。
子どもたちは今日も、自分のペースで小さな世界を広げています。
~おこさまは今、何に夢中ですか?~

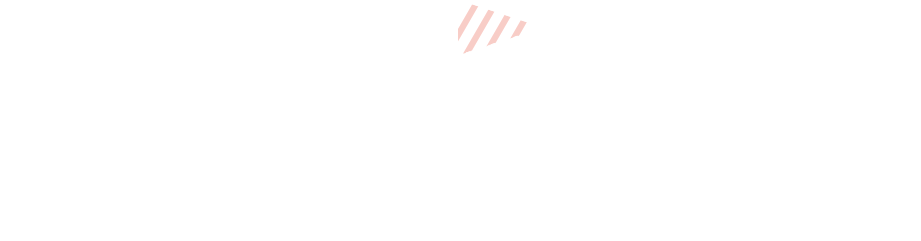
3月22日(土)お別れ会
2025.03.26

いつもと違う雰囲気に、ちょっぴり恥ずかしい(*ノωノ)




大型絵本を見たり、

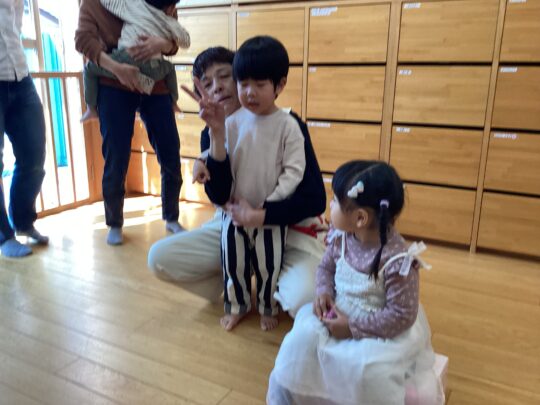
椅子取りゲームをしたよ!

それから、思い出ムービーを見て、ホロリ…😢


プレゼント渡し。



わーい!なにかな?(^^♪
笑顔がこぼれます♪



みんなで記念撮影しました!

大好きだよ!また遊びに来てね~♪

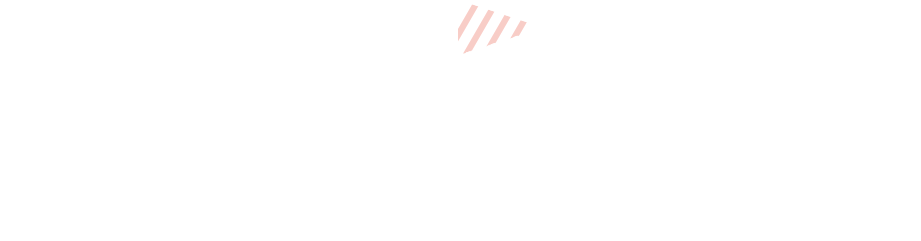
1月25日(土)みんなで遊ぼう③
2025.01.27
お店屋さんごっこだよ~
お店の人になって、お料理を作ったり、お店でお買い物を楽しんだり、
手作り楽器のお部屋では、いろんな音遊びや、パズルをしたり、おもちゃがいっぱい!!
入口には、しゃべる自動販売機が!!


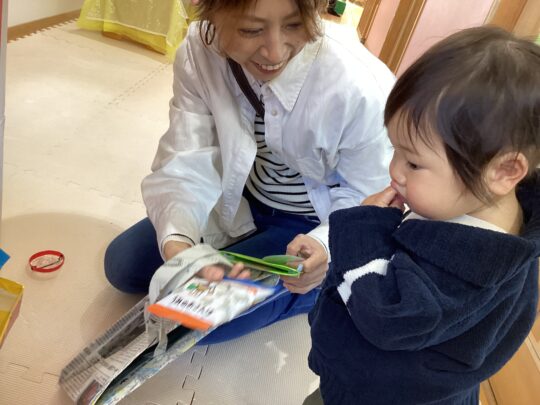
さあ、どれから遊ぶ?
<お弁当屋さん>


「どれにしますか?」 「おにぎりください♪」


<アイスクリームやさん>

「何味いいかな~」「ままは、どれがすき?」

<お蕎麦屋さん>


「トッピングはなににする?」
<おもちゃ屋さん>

「どれにしょうかなぁ」

「これ、くださ~い!」

「お店屋さんになるのもいいなぁ」


<音遊びコーナー>




なんと!アンパンマンと、バイキンマンも遊びに来たよ!!


楽しい一日となりました♪
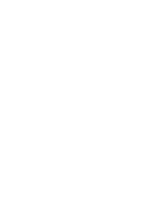

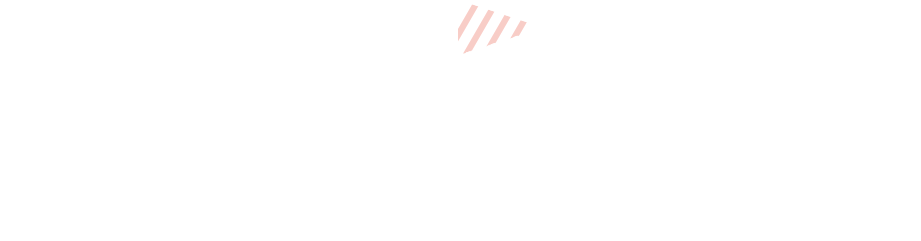
みんなで遊ぼう②11/30(土)
2024.12.02
楽しいあそびがいっぱい!!

ひよこ組では、『ボールプール』や『ぽっとん落とし』など、握る、丸める、つまむ、入れるなど、微細運動や感覚統合遊びなどができる楽しい遊びがいっぱい。


くるくる丸めて、飾ってみよう!




あおむしさん、はいったねぇ♡

うさぎ組では、トランポリンや、橋を渡ったり、飛び石を渡ったりと、粗大運動や感覚統合遊びがいっぱい!

両足ジャンプで、ぴょんぴょんぴょん!



上手に渡っていますね。

うんしょっ、うんしょっ、トンネルもくぐれるよ!
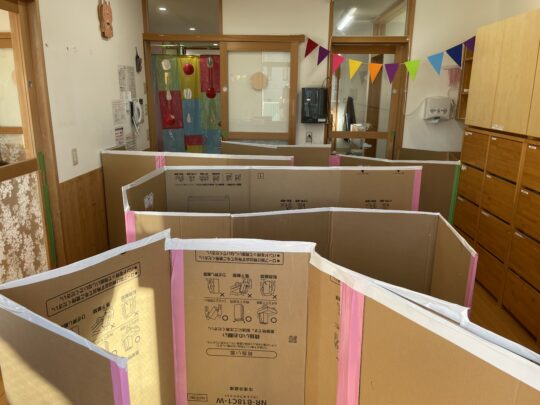
りす組は、迷路!

さあ、お母さんはどこかな?



あ、いきどまり…💦

廊下も、ワクワクがいっぱい!



「ばあっ😊」

大好きな消防車にのって、はい チーズ!


いっぱい遊んで楽しかったね!
お母さん、お父さんも、ご参加ありがとうございました😊

[龍馬学園教育グループ]
学校法人 やまもも学園

COPYRIGHT@SAKURA HOIKUEN ALL RIGHTS RESEVED.